2025年のリフォーム市場では、住宅建材や設備機器の値上げ、建築基準法の改正、省エネリフォームの補助金など、様々な要素がリフォーム費用に影響を与えております。特に、大手住宅設備メーカーが機器の価格改定を予定しており、2025年4月1日以降にリフォームを検討している場合は、値上げの影響を考慮する必要があります。では具体的にどのくらいの値上げを想定されるのか見ていきましょう。
【住宅建材・設備機器の値上げ】
住宅設備機器最大手のLIXILは、2025年4月1日からほぼ全商品にわたり値上げを発表しており、トイレ機器で平均23%、ユニットバスで平均6%、キッチンで平均6%、洗面で平均40%の値上げされています。TOTOも2025年10月1日より住宅設備機器商品の希望小売価格を改定する予定となっております。
★少しでも修繕費用を抑えるために★
補助金制度を活用することで、一部のリフォーム費用を抑えることができます。補助金の要件や申請方法などを事前に確認し、補助金の恩恵を受けられるようにしましょう。
【子育て支援型共同住宅推進事業】
国土交通省では、共同住宅(賃貸住宅及び分譲マンション)を対象に、事故防止や防犯対策などの子どもの安全・安心に資する住宅の新築・改修の取り組みや、子育て期の親同士の交流機会の創出に資する居住者間のつながりや交流を生み出す取り組みに対する支援事業である「子育て支援型共同住宅推進事業」を実施しています。ファミリー物件のみが対象にはなりますが、制度を理解しご自身の所有物件が対象になるかどうか確認してみましょう。
≪申請期間≫
令和7年4月1日(火)~令和8年2月27日(金)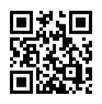
※予算執行状況により応募期間を前倒しして終了する場合があります。なお、申請に先立ち事前審査が必要となります。詳細は右記QRコードより専用HPをご覧になってください。
≪主な要件≫
・建築基準法上の共同住宅または長屋に該当する建物
・補助を受ける住戸の居住者が特定子育て世帯※であること ※令和6年4月1日時点で小学生以下の子どもを養育している世帯
・新規入居者募集の際は3か月間特定子育て世帯に限定して募集を行い、少なくとも10年間は入れ替わりの際も同様の募集とする
・住戸部分の床面積が40㎡以上
・建物が新耐震基準に適合している
弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 大橋 良二 氏
昨今では、高齢者・障がい者・低所得者等の賃貸住宅入居を円滑に進めることが重要な課題となっています。これまでオーナー側のリスク(孤独死、家賃滞納、残置物問題など)が受け入れ障壁となっていましたが、これらの不安を解消し、賃貸供給促進を図るため、住宅セーフティネット法等の改正が行われ、2025年10月に施行予定です。
【改正内容】
1.要配慮者(高齢者、障がい者、低所得者等)が円滑に入居できる市場環境の整備
・終身建物賃貸借契約の活用促進
入居者死亡後も契約更新不要で円滑な継続利用が可能に。手続きの認可手続きも簡素化されます。
・残置物処理の推進
入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、居住支援法人への委託により、死亡後の残置物処理がスムーズに実施できるよう制度が整備されます。
・家賃債務保証業者の認定制度新設
要配慮者専用に利用できる認定保証業者の仕組みを導入し、保険制度などにより保証リスクを低減します。
2.居住支援法人等による入居中サポートの強化
・居住サポート住宅制度の創設
居住支援法人等が見守り支援、福祉サービスとの連携支援を行う「居住サポート住宅」制度を創設。
・生活保護受給者の家賃支払いについては、オーナーへの直接支払い(代理納付)を原則とし、家賃滞納リスクを軽減。
・家賃債務保証の原則利用
要配慮者が新規入居する際には、認定保証業者による保証契約の利用が原則化されます。
3.住宅施策と福祉施策が連携した地域支援体制の強化
・地域単位での居住支援協議会設置促進
市区町村による居住支援協議会の設置を推進。住宅と福祉関係者の連携による包括的支援体制を整備します。
○オーナーが押さえておくべきポイント
これからは高齢者等を対象とした賃貸借契約について、法改正により制度がかわります。高齢者等との賃貸借契約の締結が社会課題とされており、今後、法改正により国が要配慮者の賃貸住宅の確保について供給を促進していく流れであることを押さえておきましょう。
【参考文献】
・国土交通省・厚生労働省「住宅セーフティネット法等改正資料(令和6年6月5日公表)」
・全国宅地建物取引業協会連合会「住宅セーフティネット法改正コラム」
2025年の賃貸市場は、成約家賃の上昇が顕著で、地主様にとって新たな土地活用の好機を迎えています。特に、都心部だけでなく郊外においても賃貸需要が高まっており、適切な戦略が収益最大化のカギとなります。
【市場の動向:家賃上昇と郊外需要の拡大】
近年、都心部の家賃高騰が続く中、通勤に便利な郊外エリアへの需要が拡大しています。これは、都心の賃料が支払い能力の限界に達しつつあるという見方もあり、今後もこの傾向は続くと考えられます。ファミリー層においても、新築分譲住宅の価格高騰を背景に、購入を断念し賃貸を選ぶケースが増加しています。これにより、ファミリー向け賃貸物件の家賃は大幅に上昇しており、地域によっては前賃料から20%ものアップで成約する事例も見られます。
【賃貸需要を捉える土地活用のポイント】
①郊外エリアのポテンシャルを活かす:
都心へのアクセスが良い郊外の土地は、手頃な家賃で広めの住空間を求める層に響きます。
②ファミリー層への対応:
分譲住宅市場からの流入が増えているファミリー層のニーズに応える物件づくりが重要です。
③外国人需要への対応:
近年、ビジネス目的で来日する外国人駐在員や技能実習生の増加が賃貸市場に影響を与えています。
【土地活用で長期的な成功を】
家賃相場の上昇は一時的なものになる可能性も指摘されていますが、多様化する入居者ニーズと、それに対応する物件供給のバランスが今後の鍵となります。地主様がお持ちの土地の特性を最大限に活かし、市場の動向に合わせた賃貸住宅を建てることは、安定した収益確保に直結します。地域に精通した建設会社と連携することで、地域のニーズを的確に捉え、最適な土地活用プランを提案してもらうことが可能です。地域に貢献し、かつ高収益を期待できる土地活用について介護福祉建築など弊社から様々な土地活用商品のご提案もさせていただきますので、是非、ご相談下さい。
※参考:賃貸住宅新聞
使われなくなった集合住宅を、新たなニーズに合わせて再生する土地活用が注目されています。特に、増加する留学生向けの学生寮としての活用は、安定した収益と地域貢献を両立させる可能性を秘めています。
【遊休資産を学生寮へ:A社の事例】
ある企業A社は、かつての集合住宅を、近隣の大学と連携し、留学生向けの学生寮として再生しました。これはA社にとって、一棟単位で学生向けに提供する初の試みとなりました。
【留学生ニーズに合わせたリノベーション】
この再生事業の成功の鍵は、大学からの要望を詳細にヒアリングし、留学生のニーズに合わせたリノベーションを行った点にあります。セキュリティ強化: 初めて来日する留学生、女性が多いことを考慮し、テレビモニター付きインターホンを全戸に設置しました。
通信環境の整備:母国の家族との連絡を考慮し、Wi-Fiを完備しました。A社は、地域のニーズに合わせたリノベーションの準備を進めていたタイミングで、大学からの問い合わせがあり、その需要に応える形で再生事業を進めたことで成功しました。
【土地活用としての展望】
この事例は、使われなくなった集合住宅や遊休資産を、変化する社会のニーズに合わせて有効活用できることを示しています。特に、留学生人口の増加は、今後の土地活用における大きな可能性を秘めています。地主様がお持ちの土地や既存物件も、地域のニーズを把握し、柔軟な発想で再生することで、安定した収益源となるだけでなく、地域貢献にもつながるでしょう。
弊社は高齢者向けの介護施設などオーナー様の遊休地活用について様々な提案・アドバイスが可能ですので遊休地活用についてお悩みの方は弊社まで、ご相談に乗らせていただきます。
※参考:賃貸住宅新聞
税理士法人タックスウェイズ 税理士 後藤 勇輝 氏
被相続人の死亡によって取得した生命保険金(死亡保険金)が相続税の非課税となる場合と、課税される場合とがあり、その違いについてみていきます。
生命保険金の課税ルール
被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料を被相続人が負担していたものは、相続人が相続等により取得したとみなされ、課税対象となります。
ただし、保険の契約者=被相続人かつ、死亡保険金の受取人が法定相続人の場合は、「死亡保険金の非課税」という相続税の優遇措置が受けられます。
死亡保険金の非課税とは
上記の非課税に該当する場合は、次の算式によって計算した限度額までとなります。
■500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
例えば、妻1人、子ども2人の場合は法定相続人が3人ですので、
「500万円×3人=1500万円」までが非課税対象となり、相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。また、法定相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。
相続税が課税対象となる範囲
法定相続人の場合、各人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。
その相続人が受け取った生命保険金-非課税限度額×相続人の受取保険金/全ての相続人の受取保険金総額=その相続人が課税される生命保険の金額
気を付ける点は?
生命保険の死亡保険金の相続税について気を付ける点は、次の通りです。
・契約内容(契約者・被保険者・受取人)を非課税適用となるように整理しておきます。
・相続開始前に、専門家に相談して設計しておくことで、定期預金などを生命保険金に組み替えておくことが可能となります。
・相続開始後すぐに手続きが可能で、受取りまでも早いので手続きの確認をしておくとよいでしょう。
具体的な手続きは、事前に税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めて頂けるようお願いいたします。
前号より、賃貸経営を行っていく上で、オーナー様ご自身の手元に残る現金、所謂キャッシュフローを最大化することが、経営を安定させるポイントになるという内容をお伝えさせていただいております。今回は、長期的な目線でキャッシュフローを最大化するために必要な修繕の目安について解説していきます。
上の表は、前号でお伝えした物件が、仮に空室が増えた場合を想定しているものになります。3室蔓延的に空室がある状態の場合、2026年のキャッシュフローが-90万円赤字になっているのがわかります。この状態を解消するためには、空室を埋める必要がありますが、何もせずに部屋を埋めるのは難しいことが予測されます。お部屋を埋めるために、1室あたり50万円のリフォームを行い、総額150万円の投資を実施したケースを見ていきましょう。
今回はリフォームを行い、各部屋3,000円賃料をアップさせ、稼働率も95%まで改善しました。リフォームを行った2026年は修繕費150万円が発生するため、満室になっても赤字ですが、翌年以降は黒字化していることがわかります。収入は160万円アップし、投資費用の改修は増収分の賃料1年で回収できます。リフォームせずに放っておくと毎年90万円以上の赤字経営となりますが、適切なタイミングで修繕することで赤字経営を事前に防ぐことも可能です。
今回お伝えした内容は一例ですが、皆様が所有している物件の中で、空室にお困りの物件がございましたら、まだ経営状態を改善する余地がある可能性も十分にありますので、この機会にぜひ一度弊社までご相談ください。
お問合せ先
土地活用相続対策研究会
株式会社野田建設